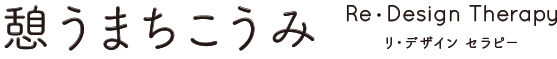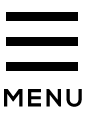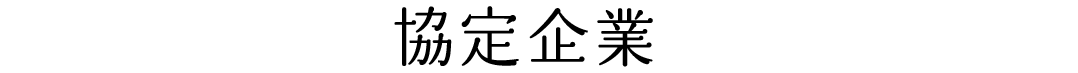-
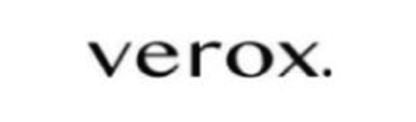
私たちは、2019年に創業した若い会社です。 「多彩な個が集まる場所から、ココロ動かすモノやコトの創造を」 私たちはこれまでの経験で得た知識-財産-をより多くの方々と共有し、デザインを通してお客様の抱える様々な問題を共に解決してまいります。 社会多様化-Diversity-を根幹とし、「モノ作り」や「コト作り」の新たな価値をご提供いたします。VEROX.に集う人々が時には学び、時には討論し、時には楽しむ新たな出会いを大切に、「共に仕事がしたい」と心から思っていただける集団でありたいと考えます。
-

日本電算企画株式会社は、1977年の創業以来、中央省庁・独立行政法人向けを中心とした高度なシステムインテグレーションサービスを提供して参りました。
弊社は予てより積極的に働き方改革を実践しておりましたが、コロナ禍を機に更なる働き方改革の一環として、ワーケーションも取り入れようとしましたところ、今回「憩うまちこうみ」と出会いました。
小海町を含む“みなみさく”の豊かな自然、美味しい食べ物などは素晴らしく、更に、素敵な地域住民の方々との触れ合いを通して、社員の健康増進、双方の活性化に少しでも貢献できれば良いと考えております。
-

弊社は、SOMPOグループの経営理念のもと「万が一の備え」と「毎日の健康」の双方でお客さまのお役に立てる存在として「健康応援企業」への変革を進め、保険本来の機能としての保障に、お客さまの健康をサポートする機能を組み合わせた新たな価値「保険+健康応援」(Insurhealth:インシュアヘルス)を提供しています。
「憩うまちこうみ」事業の発展と共に持続可能な社会の創生と地域社会の活性化に貢献していきたいと考えています。
-
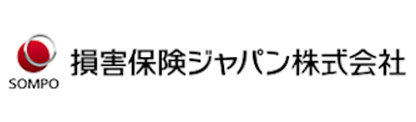
SOMPOグループは「お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献」することを実現するために、その原動力である社員と家族の心と体の「健康」が大切であるとの考えに基づき、社員の健康維持・増進を経営の重要なテーマと位置づけ、健康経営に取り組んでいます。
損保ジャパンは、小海町の素晴らしい魅力や特徴を活かした「憩うまちこうみ」事業の発展と、持続可能な社会の実現、地域社会の活性化のため、更なる「健康経営の推進」を目指してまいります。
-

当健康保険組合は、心身の健康には「適度な運動」「バランスのとれた栄養・食生活」「心の状態のメンテナンス」が特に重要と考え、加入事業所と連携して加入者のために様々な健康づくり活動に取り組んでいます。
憩うまちこうみの人・自然・食などの魅力溢れる資源を積極的に活用させていただき、加入者の更なる健康増進を目指すとともに、小海町の発展に少しでも寄与できれば幸いです。
-
 当金庫は、長野県の東信地域を主な事業区域として、地元の中小企業者や住民が、お互い
に助け合い、お互いが発展していくことを共通理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。事業や生活の繁栄のお手伝いと共に、地域社会の一員として、地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的繁栄を目指しています。
「憩うまちこうみ」事業の発展と共に地域の活性化に少しでもお役に立てればと考えています。
当金庫は、長野県の東信地域を主な事業区域として、地元の中小企業者や住民が、お互い
に助け合い、お互いが発展していくことを共通理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。事業や生活の繁栄のお手伝いと共に、地域社会の一員として、地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的繁栄を目指しています。
「憩うまちこうみ」事業の発展と共に地域の活性化に少しでもお役に立てればと考えています。
-

わたしたちは1964年の創業以来、50年以上の間、ICTサービスをご提供し続けております。
【0.5歩先のビジネスを見据えて世の中のしくみをつくり、多くの人が夢を抱ける未来を創る】をミッションとし、【人】を大切にし、【人】が育つ環境を整え、魅力的な人材を育成することに邁進しています。
弊社『佐久ソフト開発センター』がある小海町の『憩うまちこうみ』に賛同し、更なる共生を目指してまいります。 -

弊社は福井県鯖江市に本社兼工場を置き、全国の直営店で木製デザイン雑貨を販売しています。
企業理念は「ものづくり ひとづくり 感動づくり」です。
この度はご縁があって、小海町に出会うことができました。
大自然の魅力あふれる小海町の素晴らしさを多くの方に知っていただけるように「感動づくり」で地域活性のお手伝いをできればと考えております。 -

弊社は、1988年の創業より社員が仕事と生活のバランスを図り、健康で人間らしい人生を送れることを目指して設立されました。
今回の憩うまち協定を通して、小海町の豊かな自然と熱い気持ちと暖かい心をお持ちの町の方々、志を同じくする他の協定企業様と交流する中で、関係者する人々の活力と感性を活性化させ、豊かな人生を送れる会社を目指していきます。 -

弊社ではかねてより『人間尊重』、『お客さまと共に成長する社員と企業』を理念としております。
その実現のためには社員の心身の健康を維持・促進する環境をつくることが重要だと考えております。
憩うまちこうみ“が提供する「気づき」と「癒し」を上手に取り入れた「Re・Designセラピー」を社員研修や福利厚生の場で、部署や世代を越えて多くの社員に気軽に利用してもらえるよう推進していきたいと思います。